スキルタクソノミーとは?AIで進化する「個の価値」を最大化し、コラボレーションを生む方法

「Excelで管理しているスキルマップが、いつの間にか更新されなくなってしまった…」 「全社でリスキリングを推進したいが、そもそもどんなスキルがどこに不足しているのか、正確に把握できていない」 「せっかく導入したタレントマネジメントシステムが、スキルの“見える化”だけで終わってしまっている」
人事、特にタレントマネジメントや組織開発に携わる方であれば、こうした「スキル管理」の根深い課題に、一度は頭を悩ませたことがあるのではないでしょうか。
こうした課題は、もはや一企業の問題ではありません。経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート2.0」でも指摘されている通り、持続的な企業価値の向上には、経営戦略と連動した人材戦略への変革が不可欠です。その中核をなすのが、社員一人ひとりのスキルや経験といった「人的資本」の可視化と最大化に他なりません。 (出典:経済産業省「人材版伊藤レポート2.0」 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf )
この大きな潮流の中で、解決策の鍵として今まさに注目を集めているのが「スキルタクソノミー」です。
これは単なる人事管理の新しいトレンドワードではありません。スキルタクソノミーは、形骸化しがちなスキル管理を次のステージへと進め、社員の「掛け合わせ」によって新たな価値を創造するための、いわば「未来の組織を作るための設計図」と言えるでしょう。
この記事では、スキルタクソノミーの基本から、AIの活用によって「管理」を「価値創造」へと進化させる最新のアプローチまで、具体的なステップと共に解説していきます。
スキルタクソノミーが重要視される3つの背景

スキルタクソノミーの重要性が高まっている背景には、現代の企業が避けては通れない、構造的な変化があります。人事の最前線にいる皆様にとっては、日々実感されていることかと存じますが、ここでは客観的なデータも交えながら、その背景を改めて整理します。
背景1:DXと事業変革への対応
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、もはや一部のIT企業だけのものではありません。AI、データサイエンス、クラウド技術といった最先端のスキルはもちろん、既存事業のビジネスモデルを変革するためのスキルが、あらゆる業界で求められています。
実際、IPA(情報処理推進機構)が発行した「DX白書2023」によれば、DXを推進する上での課題として「人材の量の不足」を挙げる企業は、大企業・中小企業ともに半数を超えています。多くの企業が、事業変革の必要性を感じつつも、それを実行する人材の確保・育成という共通の壁に直面していることがわかります。 (出典:IPA「DX白書2023」 https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/dx-hakusho-2023.html )
自社の事業戦略と照らし合わせて、「今、どんなスキルが決定的に足りないのか」「誰をリスキリングすれば、そのギャップを埋められるのか」。そのギャップを正確に把握し、戦略的な打ち手を講じるための客観的な物差しとして、スキルタクソノミーが不可欠になっているのです。
背景2:ジョブ型雇用の広がりと人材流動化
年功序列や終身雇用といった従来の日本型雇用から、職務(ジョブ)の内容と責任範囲を明確にし、その職務を遂行できるスキルを持つ人材を登用・評価する「ジョブ型雇用」へとシフトする動きは、今後さらに加速していくでしょう。
株式会社リクルートが2023年に実施した調査では、日本企業においてジョブ型人事制度を「導入済み」と回答した企業が21.2%、「導入を検討している」が28.4%に上り、約半数の企業がジョブ型への移行を視野に入れていることが示されています。 (出典:株式会社リクルート「企業の人材マネジメントに関する調査2023」 https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2024/0423_14242.html )
このジョブ型雇用を効果的に機能させるための大前提が、「求めるスキル」の明確な定義、すなわちスキルタクソノミーです。採用の精度向上はもちろん、社内公募やサクセッションプランといった、社内の人材流動性を高める施策においても、その基盤となります。
背景3:リスキリング・学び続ける組織への変革
変化の激しい時代、企業の競争力は、社員一人ひとりが自律的に学び続け、スキルをアップデートし続ける「学習する組織」になれるかどうかにかかっています。
この変化の速さは、世界経済フォーラム(WEF)の「仕事の未来レポート2023」でも示唆されています。同レポートによると、今後5年間で労働者に求められるスキルのうち、実に44%が変化すると予測されており、既存のスキルの陳腐化がいかに速いかがうかがえます。 (出典:世界経済フォーラム「The Future of Jobs Report 2023」 https://jp.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/ )
ただ会社が「リスキリングが重要だ」と号令をかけるだけでは、社員の学習意欲は長続きしません。スキルタクソノミーによって会社が目指すスキルの方向性と、自分自身の現在地が可視化されて初めて、社員は具体的なキャリアパスを描き、「次はこれを学ぼう」と主体的な一歩を踏み出すことができるのです。
混同しやすい関連用語を整理!スキルマップやコンピテンシーとの違い

スキルタクソノミーについて議論する際、いくつかの関連用語が登場します。特に「スキルマップ」や「コンピテンシー」は混同されやすいため、ここでそれぞれの違いを明確にしておきましょう。これらの関係性を正しく理解することが、効果的な施策を設計する上で非常に重要になります。
「辞書」と「地図」の関係で理解するスキルタクソノミーとスキルマップ
スキルタクソノミーとスキルマップは、よく「辞書」と「地図」の関係に例えられます。
- スキルタクソノミー = スキルの「辞書」
- 組織内のあらゆるスキルを定義し、体系化したものです。どんなスキルが存在し、それぞれがどういう意味を持つのか、という「定義」そのものを指します。
- スキルマップ = スキルの「地図」
- スキルタクソノミーという辞書を元に、「誰が(どの部署が)、どのスキルを、どのレベルで保有しているか」を可視化したものです。人材の分布状況や、組織としての強み・弱みを明らかにする「現状把握」のツールと言えます。
つまり、まず「辞書」としてスキルタクソノミーを整備し、その共通言語を使って初めて、精度の高い「地図」であるスキルマップを作成できる、という関係性になります。
「スキル」と「コンピテンシー」の違いとは?
次に、人事の世界で長く使われてきた「コンピテンシー」と「スキル」の違いです。
- スキル = 「何ができるか」という具体的な知識や技術
- 例:「Pythonでのデータ分析」「英語での契約交渉」「半導体の回路設計」など、比較的客観的に測定しやすいものを指します。
- コンピテンシー = 高い成果を出す人の「行動特性」
- 例:「主体性」「課題解決能力」「リーダーシップ」など、成果に繋がる思考や行動のパターンを指します。スキルよりも抽象度が高く、評価が難しい側面があります。
従来はコンピテンシー評価が主流でしたが、事業環境の変化が激しい現代においては、より具体的で、事業戦略と直結させやすい「スキル」を軸にした人材マネジメントの重要性が増しているのです。
スキルタクソノミーを前提とする「スキルベース人事」
最後に、「スキルベース人事」という考え方です。これは、年齢や役職といった属人的な要素ではなく、個人が持つ「スキル」を基準に採用、配置、評価、報酬などを決定する人事の考え方を指します。
ここまで見てきたように、このスキルベース人事を実現するための大前提となるのが、客観的で、全社で合意されたスキルの定義、すなわちスキルタクソノミーに他なりません。
【3ステップで解説】スキルタクソノミーの具体的な作り方
では、実際にスキルタクソノミーを構築するには、何から手をつければ良いのでしょうか。ここでは、その基本的な3つのステップをご紹介します。
Step1: 目的の明確化(採用・育成・配置など)
最も重要なのが、この最初のステップです。「何のためにスキルタクソノミーを作るのか」という目的を明確にしなければ、後々のプロセスがすべて的外れになってしまいます。
- 目的の例:
- DX人材の採用精度を高めたい
- 次世代リーダー育成のためのサクセッションプランを策定したい
- 新規事業立ち上げに向け、社内の専門家を発掘したい
まずは目的を一つか二つに絞り、関係者間でしっかりと合意形成することが、プロジェクト成功の鍵となります。
Step2: スキルの洗い出しと定義
目的が明確になったら、次はその目的に関連するスキルを洗い出していきます。ここでのアプローチは、トップダウンとボトムアップの両面から行うのが理想的です。
- トップダウン: 経営層や事業責任者から、事業戦略上必要となるスキルをヒアリングする。
- ボトムアップ: 現場のハイパフォーマーへのインタビューや、職務記述書(ジョブディスクリプション)の分析を通じて、実際に業務で使われているスキルを抽出する。
業界団体が公開している標準的なスキルフレームワーク(例:ITSS、ETSSなど)を参考に、自社流にカスタマイズするのも有効な手段です。
Step3: 分類・体系化(グルーピングと階層化)
洗い出したスキルを、意味のある塊に分類し、体系化していくステップです。
- グルーピング: 似たスキルをまとめ、カテゴリ(大・中・小分類など)を作成します。(例:大分類「マーケティング」→中分類「デジタルマーケティング」→小分類「SEO」)
- レベル定義: 各スキルについて、習熟度を示すレベルを設定します。(例:レベル1「指導を受けながら遂行できる」~レベル4「他者に指導できる」など)
この作業は非常に骨が折れますが、ここでの分類の精度が、スキルタクソノミー全体の使いやすさを左右します。
スキルタクソノミー導入の「壁」と成功のポイント
ここまで読み進めてこられた方の中には、「理想はわかるが、実行するのは相当大変そうだ」と感じている方も多いのではないでしょうか。その感覚は、決して間違いではありません。実際に、多くの企業がスキルタクソノミーの導入プロジェクトで、いくつかの共通した「壁」に突き当たっています。
ここでは、そうした典型的な失敗例と、それを乗り越えるための成功のポイントを解説します。
よくある3つの失敗
失敗1:作成だけで力尽きる「網羅性の罠」
完璧なタクソノミーを目指すあまり、すべての職種、すべてのスキルを網羅しようとして、プロジェクトが長期化。膨大な工数をかけた結果、完成した頃にはビジネス環境が変化しており、作っただけで力尽きてしまうケースです。
失敗2:現場が使わない「形骸化の罠」
人事部門が主導で作り上げたタクソノミーが、現場の業務実態と乖離していたり、用語が難解だったりして、現場の社員が「自分ごと」として捉えられない。結果として、スキル情報の更新が誰にもされなくなり、Excelファイルが静かに眠り続ける…という最も避けたいパターンです。
失敗3:評価が曖昧になる「客観性の罠」
スキルの評価を従業員の自己申告だけに頼ってしまうと、客観性が担保できず、人によって評価基準がバラバラになってしまいます。「とりあえず全部レベル4にしておこう」といったことがまかり通ると、データの信頼性が失われ、制度そのものへの不信感に繋がります。
成功させる3つのポイント
これらの壁を乗り越えるためには、どうすればよいのでしょうか。
ポイント1:スモールスタートで始める
最初から全社展開を目指すのではなく、まずは目的を絞り、特定の部門や職種に限定して試行する「スモールスタート」が賢明です。例えば「DX推進部門のデータサイエンティスト」など、重要度と緊急度の高い領域から始め、成功体験を積み重ねながら、徐々に全社へと展開していくアプローチが成功率を高めます。
ポイント2:現場を巻き込み、自分ごと化してもらう
スキルタクソノミーは、現場で使われてこそ価値が生まれます。策定段階から現場のキーパーソンを巻き込み、彼らの言葉でスキルを定義していくことが重要です。人事はあくまでファシリテーターや標準化の支援役に徹し、現場が「自分たちのための辞書だ」と感じられるようなプロセスを設計することが、形骸化を防ぎます。
ポイント3:テクノロジー(AI)を活用する
スキル情報の収集、更新、客観性の担保といった、工数がかかりがちなプロセスに、テクノロジーの力を借りることも有効な打ち手です。特にAIを活用すれば、これまで手作業では不可能だったレベルでの効率化と、精度の高いデータ活用が期待できます。
【Beatrustの独自性】AIが実現する「価値創造プラットフォーム」への進化
そして、この「テクノロジーの活用」こそが、従来のスキル管理の限界を突破し、Beatrustが皆様に全く新しい価値を提案できる領域です。

Beatrustが提供するBeatrust Scoutでは、社員一人ひとりのスキル・経験・志向性をもとに、必要な人材を自然文で検索・発見することが可能です。
「こんな人が今ほしい」という要件を文章で入力するだけで、生成AI(特許取得済)が該当スキルを持つ人材を自動でリストアップ。検索結果をもとに、プロジェクトアサインや異動候補の選定をスピーディかつ戦略的に行えます。
人材配置が勘と経験に頼りがちだった企業でも、Beatrust Scoutの導入により、データに基づいた最適な人材活用が実現しています。
Beatrustに関する詳細はこちら:https://corp.beatrust.com/
まとめ
この記事では、スキルタクソノミーの基本から、その構築における課題、そしてAIによってその可能性を最大限に引き出す未来像までを解説してきました。
これからの時代に求められるスキルタクソノミーは、もはや人事部門が管理・維持するためだけの静的な「辞書」ではありません。
それは、社員一人ひとりの隠れた才能や情熱を「タグ」として可視化し、そのユニークな「掛け合わせ」を誘発することで、予測不能な「コラボレーション」を組織の隅々で生み出していく、動的なプラットフォームです。
AIという強力なパートナーを得て、スキル管理は、管理の時代から、価値創造の時代へと大きな一歩を踏み出そうとしています。
皆さんの会社に眠っている、まだ見ぬ才能の掛け合わせ。 それを解き放ち、新たな事業価値へと変えていく旅に、少しでも興味をお持ちいただけたなら幸いです。
関連記事

チームコラボレーションとは?組織の壁を越えて共創を生む最新アプローチ
この記事では、チームコラボレーションの基礎から、なぜ多くの企業でそれが機能不全に陥るのか、そして、それを乗り越えて「組織の壁を越えた共創」を実現するための最新アプローチについて詳しく解説します。
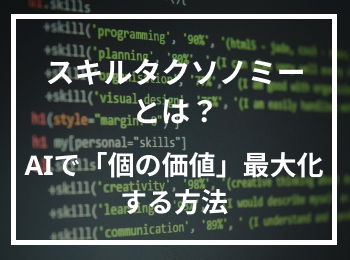
スキルタクソノミーとは?AIで進化する「個の価値」を最大化し、コラボレーションを生む方法
この記事では、スキルタクソノミーの基本から、AIの活用によって「管理」を「価値創造」へと進化させる最新のアプローチまで、具体的なステップと共に解説していきます。

スキル管理とは?目的・メリット・AIで「見える化」する最先端手法
本記事では、スキル管理の基本から、なぜ今、その重要性が高まっているのか、そして多くの企業が直面する課題を乗り越えるための「AIによるスキル可視化」という最先端のアプローチまでを徹底的に解説します。


